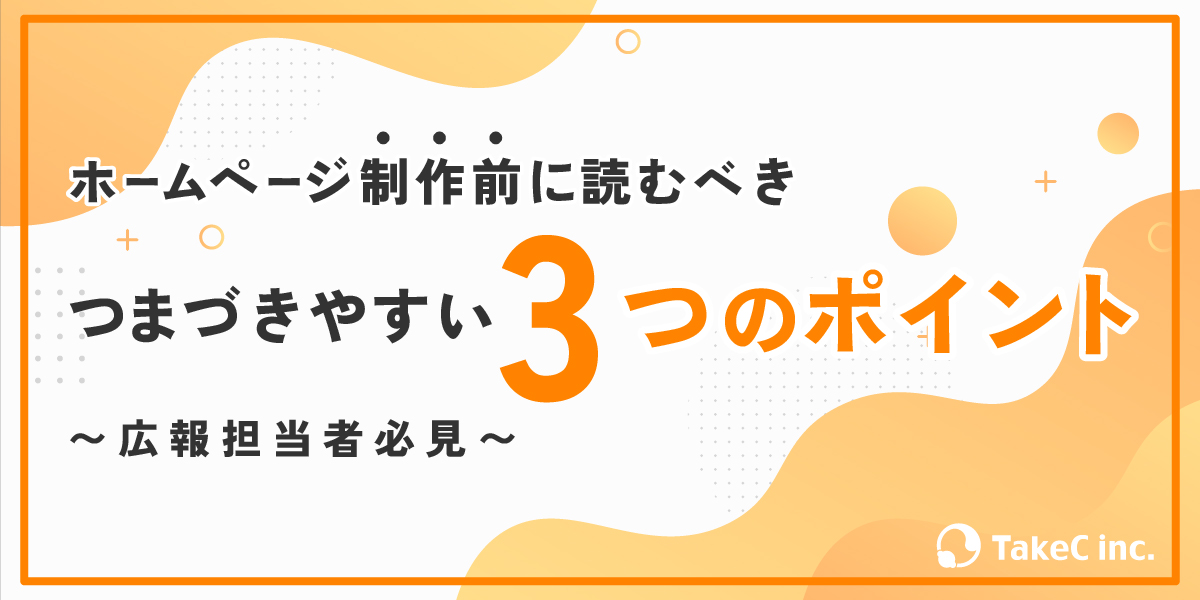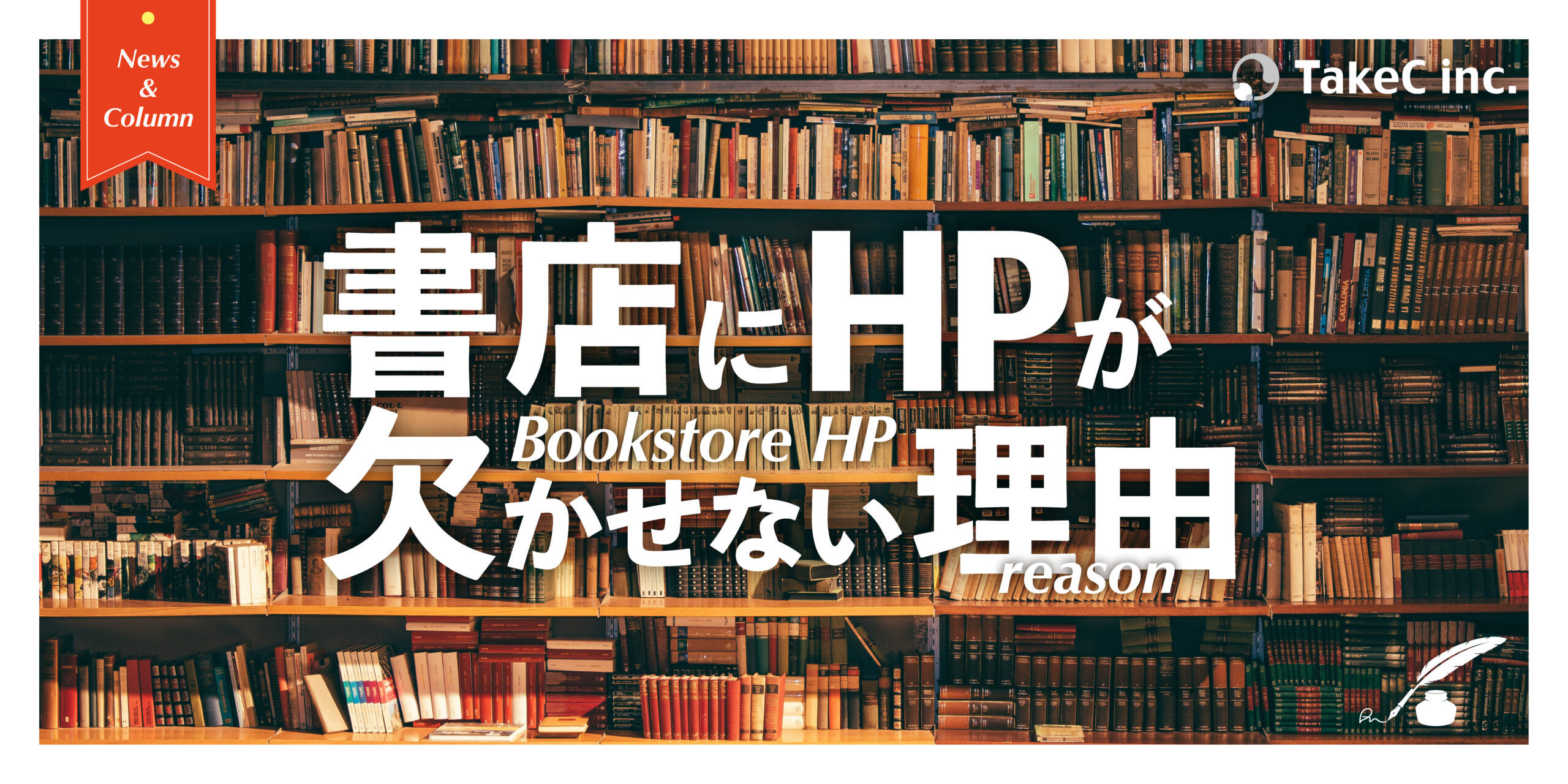NEWS&COLUMN
お知らせ&コラム
2025.10.27
WEBサイト失敗しないための「設計図」! ワイヤーフレームの作り方4ステップ
- #SEO対策
- #ホームページ
- #マーケティング
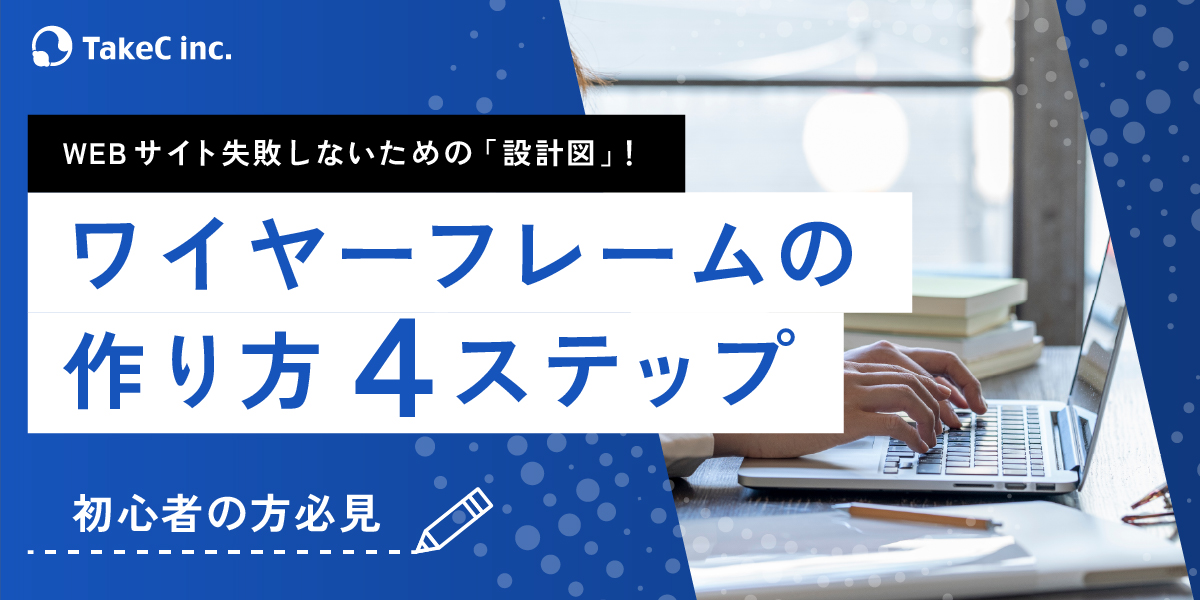
なぜワイヤーフレーム(WF)がWEB制作の成否を分けるのか
1. 制作現場で発生する「失敗」の9割は設計不足が原因
・共感と問題提起:
「デザインが上がってきてから構成変更を依頼され、納期が遅延した」
「見た目は良いが、ユーザーがどこを見ていいか分からない(CVRが低い)」
・WFの定義:
単なる画面レイアウトではなく、「コンテンツの優先順位」と「ユーザー動線」を定義する設計図であること。
WFの目的:
「誰に、何を、どのように伝え、どんな行動を取らせるか」というサイトの骨格を固めること。これを省略すると、プロジェクトの全工程で手戻りが発生する。
2. 本記事で学べること
目的達成に直結するWF設計の具体的な4ステップ。
デザイン、UX、SEOの観点から必ず押さえるべき3つの重要視点。
【基本の理解】ワイヤーフレームの役割と、デザインカンプとの違い
1. ワイヤーフレーム(WF)の役割(情報設計フェーズ)
・意思決定の土台:
クライアント、ディレクター、デザイナー、エンジニアといった関係者間の認識を統一し、議論の焦点を「情報と構成」に限定する。
・工数削減効果:
デザイン後の大幅な修正を防ぎ、制作全体の手戻り工数を最大で30%削減可能であるという事例紹介。
2. デザインカンプとの明確な違い(混同防止)
・WF:
モノクロでシンプルに。レイアウト、動線、機能に特化。
・デザインカンプ:
色、フォント、写真などビジュアル要素に特化。WFで決まった骨格に肉付けする工程。
・強調点:
WF作成時に色やデザインの議論を持ち込まないことの重要性。
制作の成否を分ける!効果的な「ワイヤーフレーム設計」の4ステップ
Step 1: 要件定義に基づく「目的」と「要素」のリストアップ
・深掘り:
サイトの最終的な事業目標(売上拡大、認知度向上など)から逆算して、このページで達成すべきKPI(重要業績評価指標)を明確にする。
例:「問い合わせ数」の増加、「記事の読了率」の向上。
要素の洗い出し:
必須要素: グローバルナビ、フッター、ロゴ、メインビジュアル、CTA(問い合わせボタン)。
コンテンツ要素: 競合分析やペルソナに基づき、「ユーザーが行動を起こすために必要な情報」を漏れなくリスト化。
Step 2: 情報の優先順位付け(ランクトーク)とグルーピング
・優先順位決定のロジック:
1.目的達成に直結する要素(CVボタン、メリット訴求):最優先。
2.ユーザーの不安を解消する要素(実績、お客様の声):高優先度。
3.付随情報・補足情報(会社概要、プライバシーポリシー):低優先度。
・専門技術「AIDA/AIDMA」の適用:
ユーザーの認知(Attention)→興味(Interest)→欲求(Desire)→行動(Action)の流れを意識し、情報を上から順に配置する。
・ワイヤーフレームへの反映:
優先度の高いブロックには、より大きな表示領域を割り当てる。
Step 3: レイアウトパターンの選定とコンテンツの配置
・基本的なレイアウトの解説と使い分け:
F型: Webサイトの標準的な視線誘導。情報量の多いブログやメディア向き。
Z型: ファーストビューでの訴求力が高い。ランディングページ(LP)向き。
シングルカラム: スマホでの操作性が高い。最近のサービスサイトで主流。
・「ホワイトスペース(余白)」の意図的な活用:
余白はデザイン要素ではなく、情報を際立たせるための重要な構成要素であることを解説。
Step 4: レビューと徹底的な検証-UX(ユーザー体験)を突き詰める
・ユーザーテストの観点:
チーム内で実際にユーザーになりきってワイヤーフレームを辿り、以下の点をチェック。
「このボタンを押した後、ユーザーはどこに遷移し、何を期待するか?」
「認知負荷(考えるストレス)が高すぎないか?」
・具体的なレビューチェックリスト(10項目例):
1.グローバルナビゲーションは全ページで一貫しているか?
2.ファーストビューでサイトの目的が瞬時に理解できるか?
3.CVボタンは導線終点以外にも、適切な位置に配置されているか?
4.スマホでの操作性を損なう要素はないか?
失敗を避ける!3つの重要視点(より詳細な設計のコツ)
視点 1: モバイルファースト設計を徹底する
・背景:
モバイルアクセスが全体の7割を超える時代において、モバイル版WFを先に作ることの絶対的な重要性を強調。
・モバイル設計の具体的な注意点:
ハンバーガーメニュー: すべての要素を詰め込まず、重要なものだけを厳選する。
固定ヘッダー・フッター: 離脱を防ぐため、重要なCTAは画面上下に固定表示させる。
視点 2: SEOを考慮した情報の構造化
・WFはSEOの基礎:
Googleのクローラーは、WFで設計された情報の優先順位と構造を読み取っている。
・具体的な施策:
見出しマークアップの仮定義: 各ブロックを$\text{H}1, \text{H}2, \text{H}3$に割り当て、キーワードが構造的に配置されているかを確認する。
内部リンク構造: 関連性の高いページへのリンクは、コンテンツの途中やサイドバーなど、適切な位置に配置する。
視点 3: テキストや画像は「実データ」で検証する
・「ここにテキストが入ります」の危険性:
デザイン工程に入ってからテキストが確定し、情報量が多すぎてレイアウト崩れを起こす原因となる。
キャッチコピーや見出しの文言は、WFの段階で仮でも具体的に入れ込み、文字数やインパクトを検証する。
・画像の検討:
挿入予定の写真やイラストのトーンが、コンテンツの流れを邪魔しないか、WFの段階で確認する。
まとめ:ワイヤーフレーム設計は、未来の成功への最も賢い投資
結論:「焦り」や「手戻り」から解放されるための設計図
ワイヤーフレーム(WF)は、WEB制作においてしばしば「面倒な作業」と見られがちです。しかし、この設計図にしっかりと時間と知恵を注ぐことは、単なる工程の一つではありません。
WFは、デザイン工程に入ってからの「やっぱりこの機能は必要だった」「この情報が抜けている」といった致命的な手戻りを防ぐための保険であり、プロジェクトの遅延や予算超過という最大のリスクを回避するための羅針盤です。
つまり、WF設計とは、制作チームとクライアントの双方が安心してゴールを目指すための、最も賢い「成功への先行投資」なのです。
メッセージ:デザインの前に、「なぜ」を語れる骨格を作ろう
「素晴らしいデザイン」や「最新の技術」はもちろん魅力的ですが、WEBサイトの真の価値は、ユーザーの課題を解決し、ビジネスの成果に貢献できるかどうかで決まります。
見た目がどんなに美しくても、ユーザーが目的のページにたどり着けなければ意味がありません。
「WEB制作」を成功に導く鍵は、高度なデザインスキルではなく、このワイヤーフレームの段階で「なぜ、この情報をここに置くのか?」「ユーザーの気持ちを考えたら、次に必要な情報は何か?」という問いと論理を突き詰めることです。
あなたがこれから挑むWEB制作において、ぜひこの設計図の質に徹底的にこだわり、成果に直結する強い骨格を作り上げていきましょう。