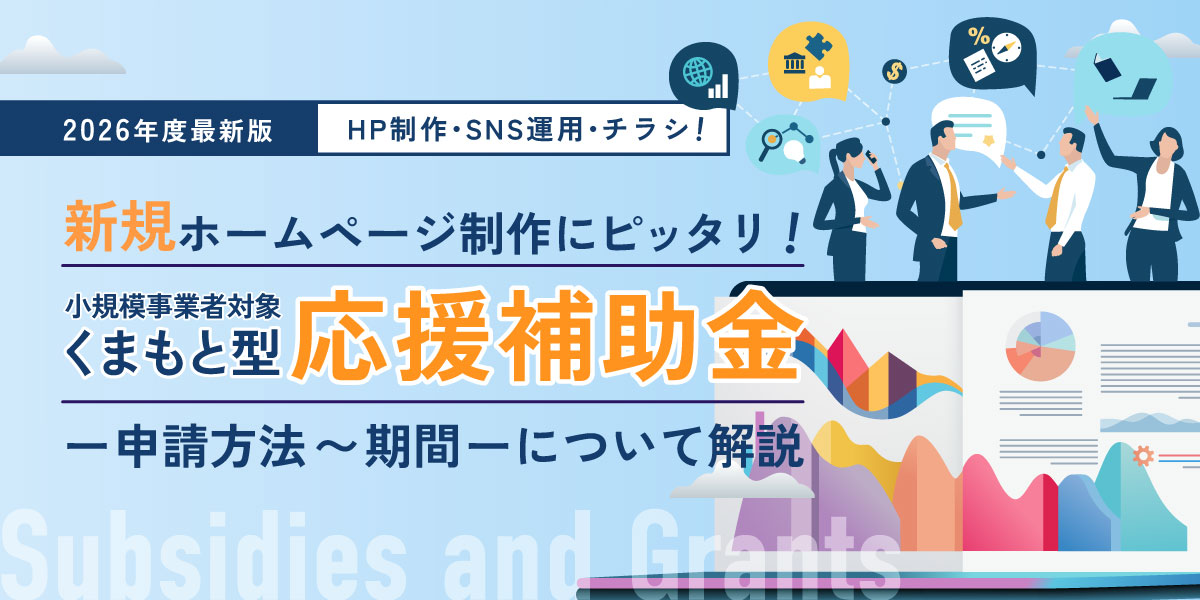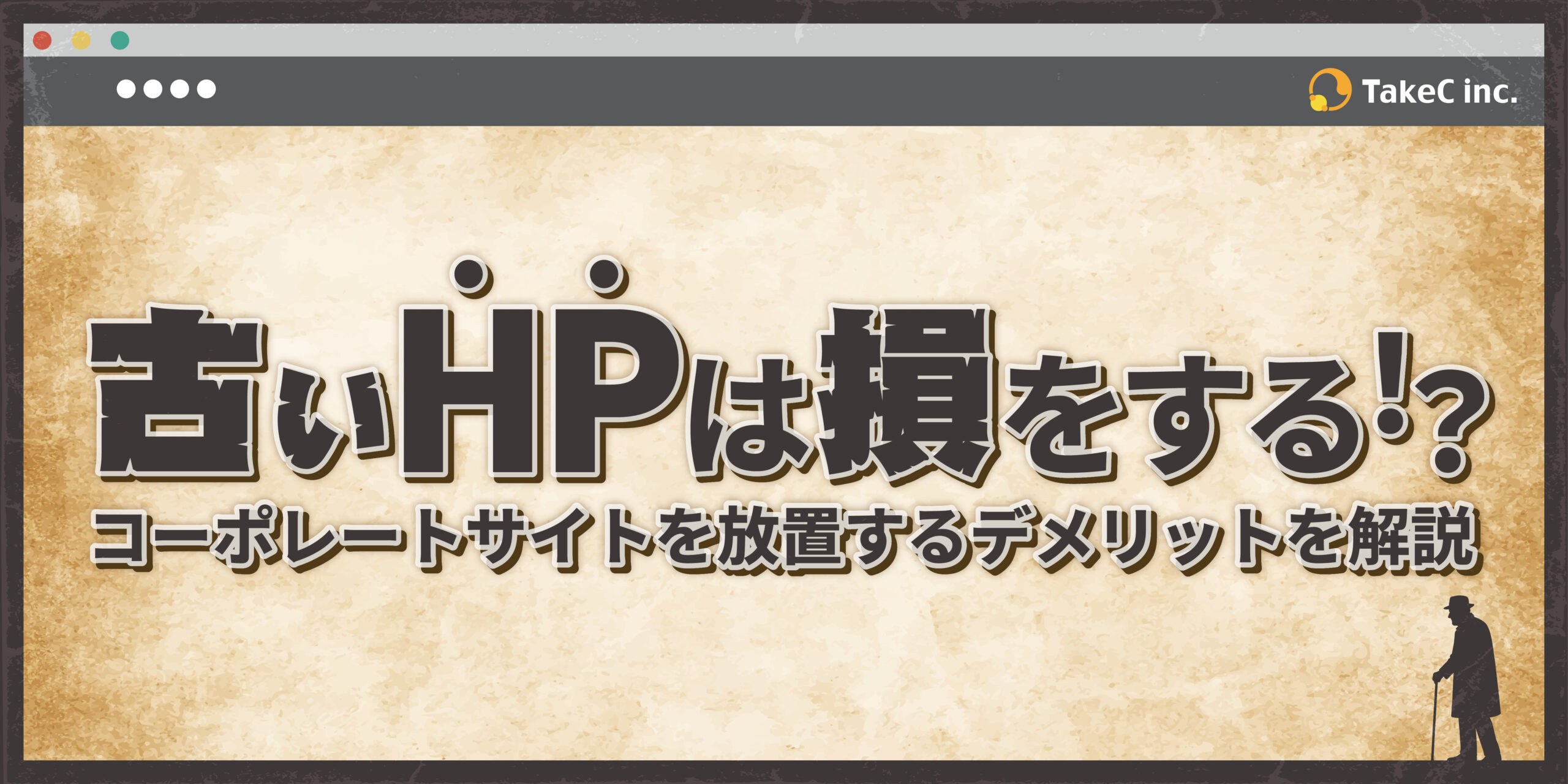NEWS&COLUMN
お知らせ&コラム
2025.09.22
弁護士や税理士事務所がHPで信頼を得るために必要なこと
- #コラム
- #デザイン
- #ホームページ
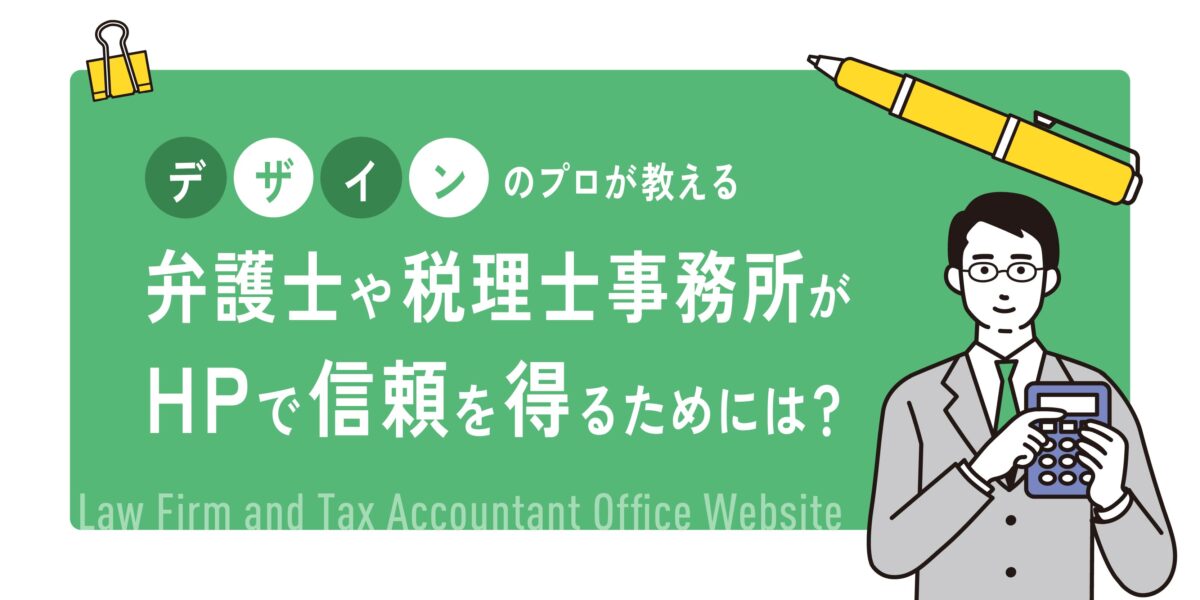
1. はじめに ― 士業にとって「信頼感」がすべて
弁護士や税理士といった士業に依頼する際、依頼者がまず求めるのは「安心して任せられるかどうか」という信頼感です。トラブル解決や大切なお金の相談を任せる相手ですから、デザインや価格以上に「この人にお願いして大丈夫だろうか」と感じられることが最優先になります。
その第一印象を大きく左右するのが、事務所の公式ホームページです。
SNSや口コミももちろん参考にはされますが、最終的に「公式の情報を見て判断したい」と考える人は少なくありません。にもかかわらず、まだまだ士業のサイトは古いデザインのまま放置されていたり、最低限の事務所概要しか載っていなかったりするケースが多いのです。これは非常にもったいないこと。
この記事では、弁護士や税理士がホームページを通じて信頼を得るために必要なポイントを、デザイン・コンテンツ・集客の観点から詳しく解説していきます。
2. 信頼感を生むデザインの基本
ホームページを開いた瞬間に感じる「雰囲気」は、依頼者にとって非常に大きな判断材料になります。
もし第一印象で「古くて見づらい」「読みづらい」と感じてしまえば、その時点で相談する意欲は大きく下がってしまいます。逆に、清潔感があり落ち着いた印象を与えるデザインであれば、それだけで安心して問い合わせをしやすくなるのです。
清潔感と誠実さを感じさせるレイアウト
士業のホームページには、派手さや奇抜さよりも「誠実でわかりやすいデザイン」が求められます。余白をしっかり取り、整然としたレイアウトを心がけることで、誠実さを表現できます。
読みやすいフォントと配色
フォントは癖の少ないものを選び、文字サイズも大きめにするのが安心です。色はブルーやグリーンなど落ち着いたトーンが信頼感を与えやすく、コーポレートカラーと組み合わせることで統一感を出せます。
顔が見えることの安心感
弁護士や税理士のプロフィール写真は非常に重要です。人は相手の顔を見た瞬間に安心したり警戒したりするものです。丁寧に撮影された写真を掲載するだけで、「どんな人に相談できるのか」がイメージしやすくなり、安心感につながります。
3. コンテンツで伝えるべきこと
デザインだけでなく、掲載する情報の内容も信頼感に直結します。依頼者が知りたいのは「この事務所は自分の問題を解決してくれるのか」ということ。そのために伝えるべきコンテンツを整理してみましょう。
経歴・資格・専門分野
弁護士であれば得意分野(離婚、相続、企業法務など)、税理士であれば担当している業務(法人税務、相続税、確定申告など)を明確に記載することが重要です。「何でも対応できます」よりも「ここに強い」という具体性があるほうが、相談者の安心につながります。
実績や解決事例
守秘義務に配慮しながら、どんな相談を解決してきたのかを紹介するのも効果的です。「年間○件以上の相続相談」「中小企業の顧問契約数○社」といった数値を出せば、説得力が増します。
スタッフ紹介
弁護士や税理士本人だけでなく、スタッフやアシスタントも紹介すると事務所の雰囲気が伝わりやすくなります。人柄やチーム感を見せることで、相談者にとっての安心材料が増えるのです。
相談の流れ
初めて依頼する人は「どういう手順で進むのか」が不安です。相談予約から面談、見積もり、契約、業務開始までの流れを図解やイラストでわかりやすく説明すると、心理的なハードルを下げることができます。
4. 安心感を演出する工夫
士業のホームページは「相談しやすさ」を演出することが大切です。
料金の明確化
「費用が不透明」という不安は大きなネックになります。最低限の料金目安や、よくあるケースの費用例を掲載することで、不安を解消できます。
Q&Aコンテンツ
「初回相談は有料?」「どんな資料を持っていけばいいの?」など、よくある質問をまとめておくと、相談のハードルを下げられます。
事務所や設備の紹介
実際の事務所の写真やアクセス方法を載せることも安心につながります。「どんな場所で相談するのか」がわかれば、初めて訪れる人も不安を感じにくくなります。
5. SEOと集客の観点から
信頼感を演出するだけでなく、検索で見つけてもらうことも重要です。
地域名+士業での検索
「新宿 弁護士」「大阪 税理士」といった地域名検索は依頼者のニーズが強いキーワードです。ホームページにしっかり地域名を盛り込み、Googleマップとの連携も意識しましょう。
指名検索で公式HPを上位表示
事務所名や弁護士名を検索したときに、公式サイトがすぐ出てこないと信頼を失います。SEO対策を行い、必ずトップに出るよう整備しましょう。
コラム記事の発信
専門性を示すために、法律や税務に関するコラム記事を定期的に更新するのも効果的です。検索流入を増やすと同時に、知識の蓄積が「この事務所は頼りになりそう」という印象を強めます。
6. デザイン会社に依頼すべき理由
士業のホームページを自作や安価なテンプレートで作るケースもありますが、それでは「信頼感」を十分に演出するのが難しい場合があります。
プロのデザイン会社に依頼すれば、写真撮影からライティング、SEO対策までトータルでサポートが可能です。単なる「見栄えのいいサイト」ではなく、「依頼者が安心して問い合わせできる導線」を設計することができます。
7.実際の成功事例から学ぶポイント
抽象的な「信頼感が大事」という言葉だけでは、なかなか具体的な改善につなげられません。そこで実際に弁護士・税理士事務所のホームページで成果を上げている事例を見てみましょう。
ある地方の法律事務所では、リニューアル前は「代表弁護士の顔写真がなく、サービスメニューもPDFの羅列」という状態でした。その結果、訪問者の直帰率は70%を超えており、問い合わせにつながることは稀でした。
しかし、リニューアル後に行った改善点は以下の通りです。
- 代表弁護士の顔写真を大きく掲載し、簡単な経歴と理念をわかりやすく紹介。
- 「初回相談無料」「24時間メール受付」など、利用者に安心を与えるキャッチコピーをトップページに配置。
- 難しい専門用語はできる限り噛み砕き、Q&A形式で解説ページを追加。
- 実績を数字で表現(例:交通事故案件300件以上、相続相談年間200件など)。
この結果、問い合わせ数はリニューアル前の 約3倍 に増加し、特に「顔が見える安心感」と「実績の明示」が反響を呼んだと報告されています。
税理士事務所の事例では、「法人向けと個人向けサービスを同じページで説明していた」ことが課題でした。そこでターゲットごとにページを分け、それぞれの悩みに寄り添った文章を追加。さらに料金シミュレーションツールを導入したことで、「料金がわかりやすい」と評判になり、新規契約が大幅に増えました。
つまり、信頼を得るためには 「顔の見える安心感」+「数字や事例による具体性」+「ターゲットに合わせた情報設計」 が欠かせないのです。
8.よくある失敗例と避けるべきポイント
一方で、士業事務所のホームページには「やってはいけないこと」も存在します。
- 難解な専門用語の多用
「被相続人」「贈与税控除」など、法律や税務に馴染みのない人にとっては理解が難しい用語を多用すると、読者はすぐに離脱してしまいます。専門性は必要ですが、利用者目線のわかりやすさを優先すべきです。 - 情報更新が止まっている
最新ニュースやお知らせの最終更新が「3年前」だと、それだけで「活動していない事務所なのでは?」と疑われてしまいます。月1回でもいいので更新を続けることが大切です。 - 自己PRばかりで利用者視点がない
「当事務所は○○年の歴史があります」「弁護士5名在籍」など、自慢話に終始してしまうと、利用者が本当に知りたい「私の問題を解決できるのか?」という視点が抜け落ちてしまいます。サービス紹介は「相手の悩みから逆算」して書くのが効果的です。 - スマホ非対応(レスポンシブ未対応)
今やスマートフォンでの検索利用は全体の7割を超えています。スマホで見づらいホームページは、それだけで信頼性を損ないます。
9.まとめ:信頼を積み重ねるホームページとは?
弁護士や税理士にとって、ホームページは「営業マン」であると同時に「名刺以上の存在」です。
信頼を得るために大切なのは、
- 誰が相談に乗ってくれるのかを示す「顔の見える安心感」
- 実績や事例、数字を使った「具体的な裏付け」
- 利用者目線でわかりやすく整理された「情報設計」
- 継続的な更新による「信頼の積み重ね」
これらを意識することで、初めて「この事務所なら安心して相談できる」と感じてもらえるのです。
士業の仕事は、一度信頼を得られれば長期的な関係に発展する可能性が非常に高いもの。だからこそ、ホームページは単なる形式的な存在ではなく、戦略的に「信頼をデザインする場」として活用することが重要です。
弁護士・税理士事務所のホームページ制作やSNS運用でお悩みの方へ
有限会社テイク・シーでは企業・店舗・施設など、幅広い分野のホームページ制作を行なっています。
また、SEO対策・WEB広告など、WEB周りのさまざまなお困りごとを丸ごとお任せいただけます。
この記事を読んで、結局何から始めればいいのか分からない…
とお悩みの方、お任せください。テイクシーがあなたのサポートをいたします。
ホームページ制作やSNS運用に関するご相談も承ります。
まずは、お気軽にご相談ください。