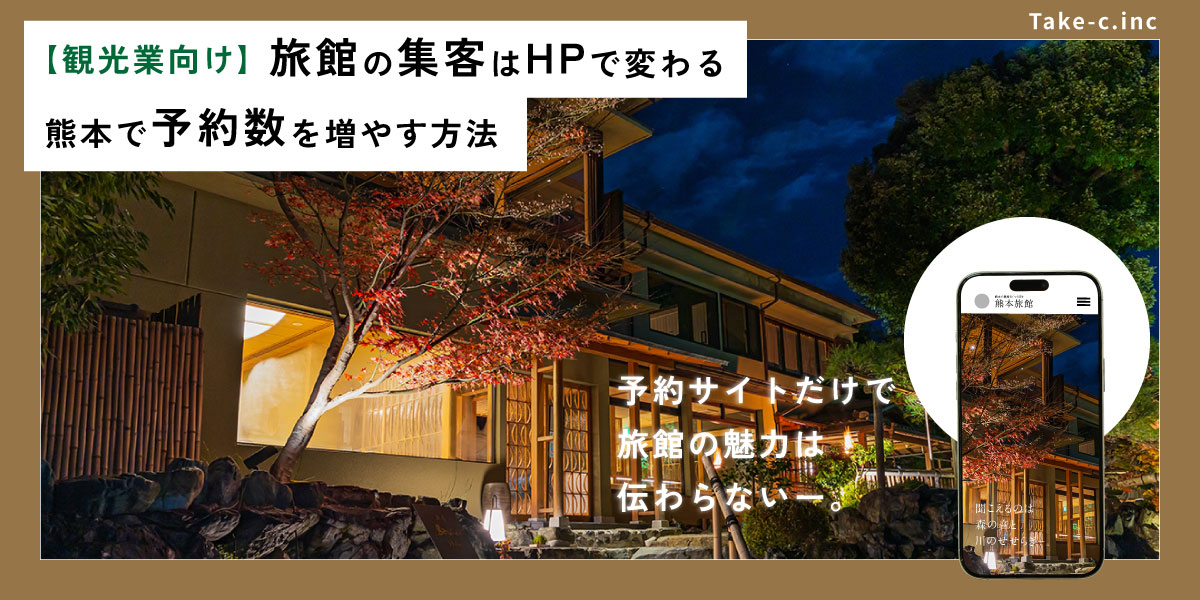NEWS&COLUMN
お知らせ&コラム
2025.07.09
建築業界にWebが必要な理由とは?〜“いい仕事”を“選ばれる仕事”にするために〜
- #コラム
- #ホームページ
はじめに
なぜ今、建築業界にWebが必要なのか?
建築業界は「技術力」「現場対応力」「信頼関係」で成り立つ業界です。職人や設計士、営業や監督が一丸となって“いい家”を作り上げる。それは今も昔も変わらない、日本の建築の強さです。
しかし、その「いい仕事」がうまく伝わらない。
SNS時代、情報があふれる中で「技術力=選ばれる理由」にはなりづらくなっています。
どれだけ丁寧な仕事をしていても、Web上で存在感がなければ、お客様には“知られない”。
この記事では、Webを活用することで得られる建築業界の“新しい可能性”について、採用・集客・ブランディングの観点から深掘りしていきます。
情報発信は「知ってもらう」ための第一歩
施工事例だけじゃ足りない時代
以前は、チラシや展示場、紹介といった“オフライン”の動線で十分でした。ですが、今のお客様はまずスマホで検索します。
「○○市 注文住宅」
「ローコスト住宅 評判」
「○○建設 口コミ」
検索結果に自社の情報がなければ、いくら実力があっても“候補にすら入らない”のです。
信頼は「情報量」と「見せ方」でつくられる
ホームページやSNSを通じて、
施工実績の豊富さ
社員の顔が見える現場紹介
お客様の声(レビュー)
アフターサービスの姿勢
といった「見えにくい部分」まで可視化することで、信頼感はぐっと高まります。
Webは“選ばれる理由”をつくるツール
他社との差別化ポイントを伝えよう
「ウチは小さな工務店だから…」
「ハウスメーカーには勝てない…」
そう感じている方も多いかもしれません。しかし、お客様にとっては“誰に頼むか”が全て。
そこでWebは、「らしさ」「こだわり」「人柄」を伝える場として力を発揮します。
たとえば
地元密着で細やかな対応ができる
無垢材や自然素材にこだわっている
社長が直接お客様対応する
といった“強み”を、コンテンツとしてしっかり伝えることで、「自分に合ってる会社だ」と感じてもらえるようになります。
採用活動にもWebは不可欠
若手が来ないのは「情報がない」から?
建築業界では深刻な人材不足が続いています。特に若年層の職人や設計士、現場監督がなかなか集まらないという声をよく聞きます。
でも、採用サイトがなかったり、社内の雰囲気が分かるようなSNS投稿がなければ、そもそも“選択肢”として認識されません。
Webで「未来」を感じてもらう
若者が重視するのは、
働いている人の雰囲気
教育体制やサポートの有無
やりがいを感じられるか
といった、“共感”や“安心感”。
そのためにも、ブログや社員インタビュー記事、現場の様子を映した動画などが大きな武器になります。
成約率アップにもWebは効く!
お客様は“予習”してから来る
Webが整っている会社には、お客様も“納得して”やってきます。
自社の強みを知った上で相談に来る
完成事例を見て、理想のイメージがある
代表の考えに共感している
こうした状態での面談は、成約率が圧倒的に高い。
一方、Webが不十分な会社は「まず会社説明から」という段階でつまずいてしまうことも少なくありません。
Web活用の成功事例(仮想ストーリー)
A社:小規模工務店の事例
地域密着・3人の小さな工務店
SNSで現場風景を定期発信
ホームページに「社員ブログ」と「施工レポート」を設置
オープンハウスをLP(ランディングページ)で告知・予約導線を設置
→ 結果:毎月3件以上の問い合わせ、地元客からの「ファン化」が進む
B社:採用強化に成功した会社
求人ページに「社員インタビュー動画」を導入
Instagramで職人の日常やDIY講座を投稿
1年で20代の応募が2倍に
→ 結果:若手採用の定着率アップ、「入りたい会社」になった
よくあるWeb導入の誤解と解決法
誤解①:「うちは昔から口コミだけで十分」
→ 口コミで来るお客様も、実はホームページやGoogleマップをチェックしています。信頼を裏付けるための情報がWebには必要です。
誤解②:「SNSは若者向けだから不要」
→ SNSは採用にも施主にも効きます。40〜50代のユーザーもInstagramやYouTubeで住宅情報を見ているのが現状です。
誤解③:「Webに詳しい人が社内にいない」
→ 外部パートナーに任せるのも立派な“内製化”。
中小企業でも、制作会社と伴走する形で成功している事例はたくさんあります。
Webは「育てる資産」
作って終わりじゃない。育てて強くする
WebサイトやSNSは、使いながら育てるものです。
現場写真の投稿
イベントのお知らせ
お客様の声の掲載
員のブログ更新
など、日々の情報発信が会社の資産になっていきます。
そして何より、“顔が見える会社”は選ばれやすいのです。
具体的に何を始めればいい?建築会社のWeb活用ステップ
「Webが大事なのはわかったけれど、何から始めればいいの?」
そう感じる建築会社の方は多いと思います。ここでは、今すぐ取り組める具体的なステップを3段階に分けてご紹介します。
ステップ①:まずは“土台づくり”
まず整えたいのが「自社の顔」となるホームページの見直しです。
✅最低限必要な要素
事業内容がわかるTOPページ
代表メッセージ(会社の想い)
施工事例の一覧と詳細ページ
会社概要・アクセス情報
問い合わせフォーム
ここで大切なのは「情報の鮮度」と「信頼感」。
施工実績が5年前で止まっていたり、スマホで見づらかったりすると、そこで離脱してしまいます。
✅改善のポイント
モバイル対応(レスポンシブ)
最新の施工事例やイベント情報を定期更新
写真のクオリティにこだわる(スマホ撮影でも工夫次第で魅せられます)
ステップ②:SNS・ブログで“継続発信”
次に取り組みたいのが発信の習慣化です。おすすめはInstagramとブログ。
Instagram(写真+短文で現場の“温度”を伝える)
現場風景・進行中の施工の様子
社員紹介(職人・監督・営業など)
イベント情報や完成見学会
DIYのコツ・リフォーム事例
📌 ポイント
「完成後」だけでなく「途中経過」も発信することで、“家づくりのリアル”を伝えられます。現場に関わる人の顔が見えると、親近感もアップ。
ブログ(SEOや共感を狙った“語り”)
家づくりの流れや注意点
よくある質問(例:予算内に抑えるコツ)
社員のつぶやき・現場エピソード
地域の情報(地元に根差した話題)
📌 ポイント
1記事800〜1,500字程度でOK。
テーマは「お客様の質問になりそうなこと」を意識すると、検索にも強くなります。
ステップ③:動画で“温度感”を伝える
さらに余裕が出てきたら、動画活用がおすすめです。特別な機材は不要、スマホでOK。
おすすめの動画例:
モデルハウスや施工現場のルームツアー
代表あいさつ・会社紹介
社員インタビューや職人の一日
お客様の声(施工後のインタビュー)
📌 ポイント
1〜3分程度の短い動画でOK。
視覚と音声で“人柄”や“現場の雰囲気”が伝わることで、より強い共感を生みます。
Web活用の先にあるもの:建築業界の未来とは?
「伝えること」は未来への投資
建築業界は、IT業界のように日進月歩ではありません。ですが、「伝える技術」だけはどの業界も同じく進化しています。
例えば、
小さな工務店がSNSでファンを集め、県外から注文が来る
現場のInstagram投稿が、採用面接のきっかけになる
YouTubeの施工動画を見て「この会社しか考えられない」と選ばれる
そんなことが、もう現実に起きています。
デジタル×建築で“地域ブランド”を築く
大手ハウスメーカーに勝つために必要なのは、知名度ではなく、共感と信頼。
地元密着の工務店や中小建設会社が、Webを活用して地域に根を張り、地域の「顔」になることができます。
Webは「拡大」のためのツールではなく、“深く伝える”ための手段。
地域の暮らしを豊かにしたい
家族が安心して暮らせる家をつくりたい
その想いを、届けたい人にきちんと伝えたい
そんな気持ちがあるなら、Webは必ず力になります。
最後に:Webは“人をつなぐ道具”である
建築業界にとって、Webは「未来のためのパートナー」です。
無理に流行を追わなくていい
派手な広告を出す必要もない
自社の強みや日々の仕事を、丁寧に、誠実に伝える
それがWebの最大の使い方です。
Webとは、ただの技術ではありません。
それは、人と人、想いと想いをつなぐ“橋”のようなもの。
これからの建築業界は、“建てる力”と“伝える力”の両輪で、もっと大きな信頼を築いていくはずです。