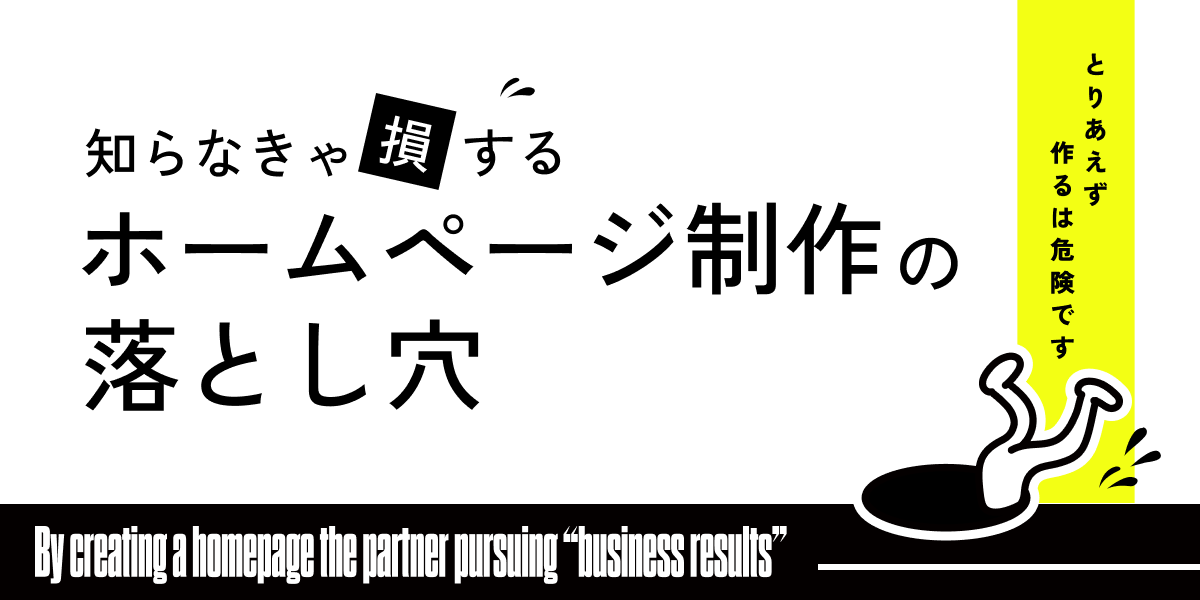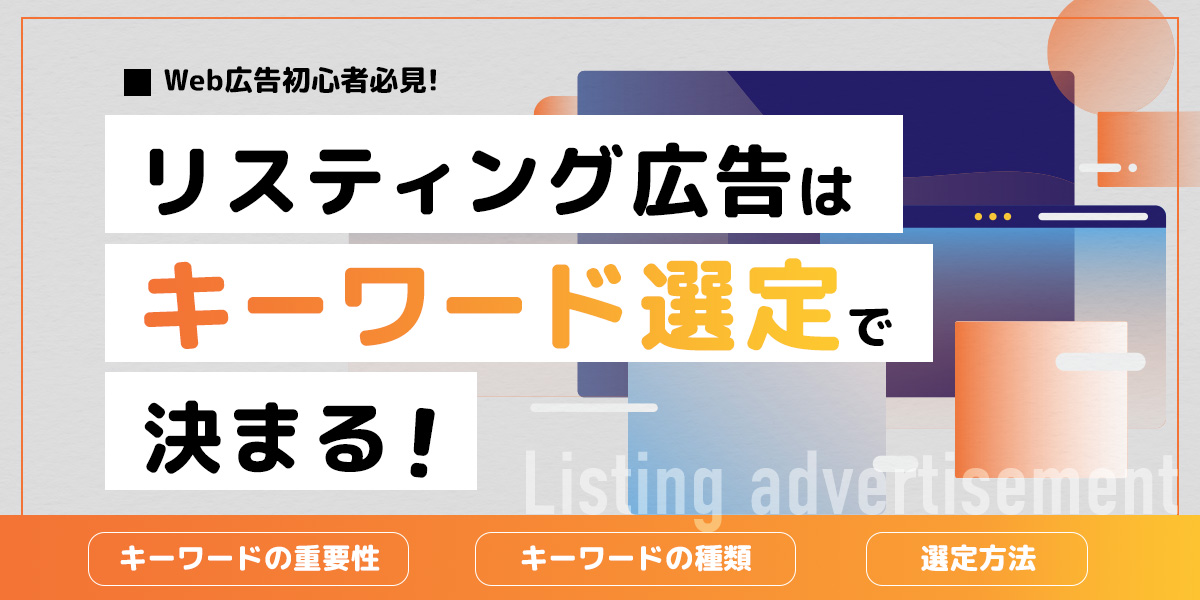【HP制作】医療系・病院がホームページを持つ最大の理由とは!
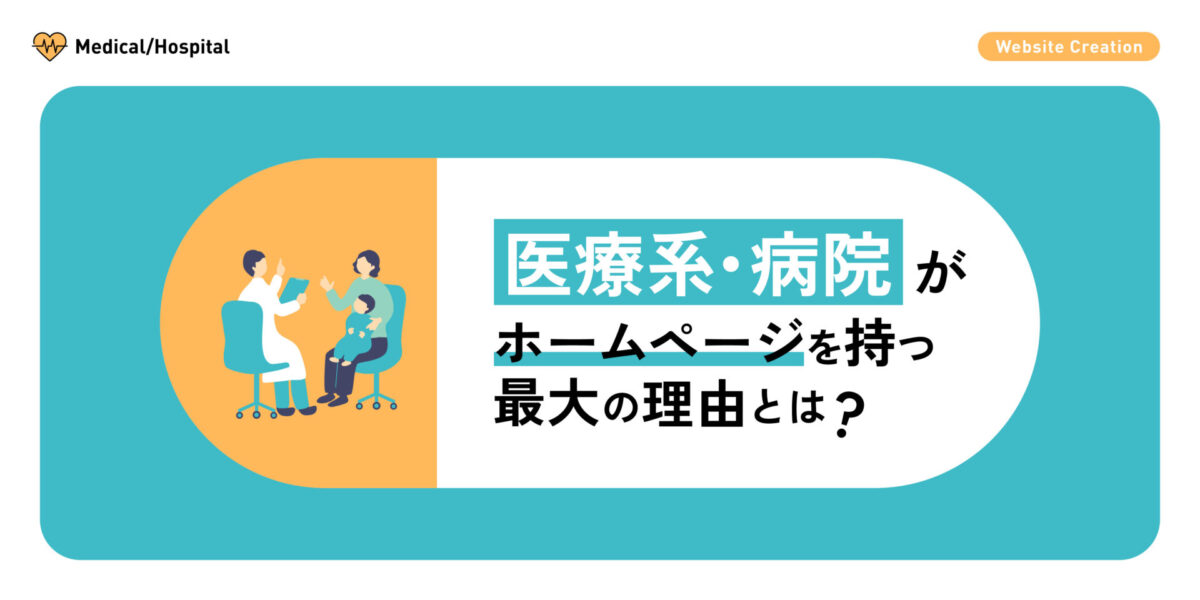
医療機関にホームページが必要な理由とは?
医療機関にとって、ホームページは「顔」です。
初めて病院を探す患者にとって、第一印象を決める存在だからです。
かつては口コミや紹介が中心でした。
しかし今は、8割以上がネット検索で病院を探します。
このときホームページがないと、患者はどう感じるでしょうか。
「この病院、大丈夫かな?」と、不安を抱いてしまいます。
つまり、ホームページはただの案内板ではありません。
患者からの信頼を得るための必須アイテムなのです。
また、情報発信の手段にもなります。
診療時間、休診日、医師の専門分野などを、正確に伝えられます。
これらをきちんと発信できるかどうかで、病院のイメージが大きく変わります。
たとえば、Aさん(30代女性)はこう話します。
「近所に内科がたくさんあります。でも、ホームページがないと怖くて行けないんです」
どんな先生なのか、院内は清潔なのか。
ホームページがないだけで、大きな不安につながっているのです。
また、総務省の調査によれば、
「医療機関の情報収集にインターネットを使う人は85%」に達しています。(※出典:令和5年通信利用動向調査)
つまり、ホームページを持たないことは、患者の選択肢から外れることを意味します。
ホームページがもたらす3つのメリット
医療機関がホームページを持つと、次のメリットがあります。
1. 信頼感を高める
患者は、病院のホームページをじっくり見ています。
医師の経歴、設備、院内の雰囲気まで細かくチェックしています。
しっかりしたホームページがあるだけで、「信頼できそう」と感じてもらえます。
逆に、情報が古かったり、そもそも存在しないと不安が膨らみます。
信頼感を得るには、最新情報をきちんと発信することが大切です。
ある小児科医院では、ホームページを刷新しただけで、新患が前年比120%に増えました。
理由は「清潔感が伝わった」「先生の顔が見えた」という安心感です。
「見た目だけでそんなに違うの?」と思うかもしれません。
しかし、第一印象はわずか3秒で決まると言われています。
ホームページも、例外ではありません。
2. 来院前の不安を減らす
初めて行く病院には、不安がつきものです。
どんな先生がいるのか、待ち時間は長いのか、駐車場はあるのか──。
ホームページにこれらの情報が載っていれば、患者は安心できます。
結果として、キャンセルや問い合わせの数も減ります。
患者の不安を取り除くことは、医療サービスの一部なのです。
たとえば、「初診の流れ」を図解で説明すると、安心感が大きく変わります。
受付〜診察〜会計までの流れがわかれば、初めての患者も迷いません。
また、院内の混雑状況をリアルタイムで表示している病院もあります。
これにより「待ち時間のストレス」が大きく減っています。
3. 採用活動にも役立つ
ホームページは、求職者向けの窓口にもなります。
若い医師や看護師は、病院選びの際に必ずホームページを見ています。
理念や職場環境をきちんと伝えれば、優秀な人材の確保につながります。
看護師専門サイト「ナース専科」の調査では、
「転職先を選ぶとき、ホームページを必ずチェックする」という人は92%に上ります。
給与や福利厚生だけでなく、病院の雰囲気・理念を知りたいのです。
これをきちんと伝えられる病院ほど、応募が増えています。
患者に選ばれる病院ホームページの特徴
では、患者に選ばれるホームページには、どんな特徴があるのでしょうか。
1. わかりやすい情報設計
必要な情報にすぐたどり着ける設計が大切です。
「診療時間」「アクセス」「診療内容」は、トップページから一目でわかるようにしましょう。
難しい専門用語はなるべく使わず、やさしい表現で伝える工夫も必要です。
「診療時間は?」「どんな科目があるの?」
こうした基本情報を探すのに、3クリック以上かかると、7割が離脱すると言われます。
トップページに、
- 診療時間
- 診療科目
- 休診日
- アクセス
これらをまとめておきましょう。
2. スマホ対応
今や、7割以上の人がスマホで病院を探しています。
スマホで見たときに、文字が読みにくかったり、ボタンが押しづらいと、それだけで離脱されてしまいます。
スマホファーストで設計することが、信頼につながります。
特に20代〜40代では、パソコンよりスマホ検索が主流です。
「スマホで見づらい病院は選ばない」という声も増えています。
デザインだけでなく、表示速度にも注意が必要です。
ページが3秒以内に表示されないと、ユーザーの53%が離脱すると言われています。
3. 写真・スタッフ紹介の充実
写真は文章以上に多くを伝えます。
院内の様子、医師やスタッフの笑顔があると、安心感が生まれます。
また、スタッフ紹介ページがある病院は、ない病院より圧倒的に好感度が高いです。
実際に、スタッフ写真を載せたクリニックでは、
問い合わせ件数が1.5倍に増えた事例もあります。
「どんな人が診てくれるのか」
これを事前に知れるだけで、来院へのハードルがぐっと下がるのです。
ホームページ制作で失敗しないための注意点
ホームページを作るとき、次の点に注意しましょう。
1. 自作で済ませない
「簡単なテンプレートで自作すればいい」と考える人もいます。
しかし、医療機関は「信頼」が命です。
プロに依頼し、デザイン・導線・コンテンツをしっかり作り込みましょう。
費用を惜しむと、逆に機会損失が大きくなります。
ある個人クリニックでは、無料テンプレートで自作しました。
結果、デザインが稚拙で、逆に患者離れを起こしてしまいました。
「安く済ませたつもりが、信頼を失った」
これでは本末転倒です。
ホームページ制作は、病院経営と直結しています。
プロの力を借りることが、結果的にコスパが良いのです。
2. 放置しない
ホームページは作ったら終わりではありません。
情報をこまめに更新しないと、すぐに古びた印象を与えてしまいます。
休診情報や診療時間の変更など、必ずリアルタイムで反映させましょう。
「3年前の休診情報がそのまま」
「院長が代わったのに、古いまま」
こうした放置されたサイトを見ると、患者はすぐに不安を抱きます。
最悪の場合、「廃業しているのでは?」と思われ、機会損失が発生します。
医療機関におすすめのホームページ活用例
単なる案内ページにとどまらず、さらに活用する方法もあります。
1. 院内ブログの発信
医師のコラムや健康情報を発信すると、患者との距離がぐっと縮まります。
SEO対策にもなり、検索順位の向上にも役立ちます。
2. 予約システムの導入
オンラインで予約できると、患者もスタッフも負担が減ります。
待ち時間の短縮にもつながり、患者満足度が向上します。
WEB予約を導入した眼科医院では、
待ち時間のクレームが激減しました。
受付スタッフの負担も減り、現場のストレスも軽減。
患者満足度とスタッフ満足度、両方が向上しました。
3. 地域連携の情報発信
地域の医療機関との連携体制を紹介すると、信頼感がアップします。
紹介先病院とのネットワークを見せることも、患者にとって安心材料となります。
健康コラムを月1回更新するクリニックでは、
検索流入が半年で150%に増えました。
「熱が出たらどうする?」「インフルエンザ予防のコツ」
こうした実用的な情報は、患者にも喜ばれます。
また、定期的な更新はSEO対策にも効果抜群です。
地域の診療所・薬局・訪問看護ステーションとの連携情報を掲載している病院は、
高齢者層からも「頼れる存在」として支持されています。
よくある質問(FAQ)
Q1. 小規模クリニックでもホームページは必要ですか?
→ 必須です。むしろ小規模ほど「見える化」で信頼を得る必要があります。
Q2. 毎日更新しないといけませんか?
→ いいえ。大切なのは「定期的な最新情報の発信」です。
月1〜2回のペースでも十分効果があります。
Q3. 制作費はどれくらいかかりますか?
→ シンプルなホームページなら、30万円前後から可能です。
集患・採用を本気で狙うなら、50〜100万円を想定しておきましょう。
まとめ:ホームページは「信頼の窓口」
医療機関にとって、ホームページは単なる「案内板」ではありません。
信頼を得るための「窓口」であり、患者との最初の接点です。
情報発信、安心感の提供、採用活動など、さまざまな役割を担っています。
「うちは小さい病院だから必要ない」と思わないでください。
むしろ規模が小さい病院ほど、ホームページの力がものを言います。
これからの時代、ホームページは「必須インフラ」です。
今すぐ、自院にふさわしいホームページを整えましょう。
📩 ホームページ制作のご相談はお気軽に!
有限会社テイク・シーでは、Webサイトから印刷物までトータルにサポートしています。
有限会社テイク・シーに相談する