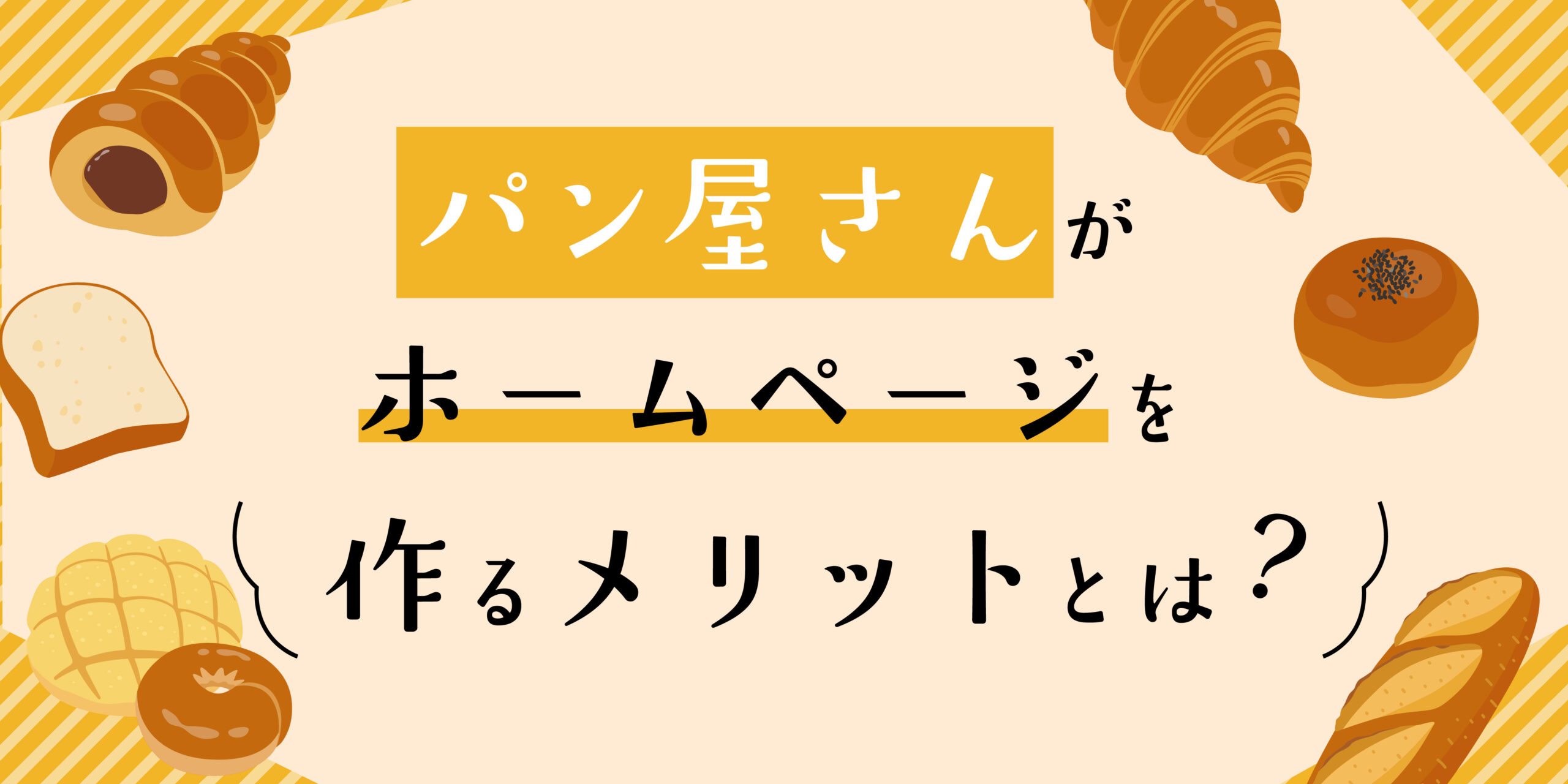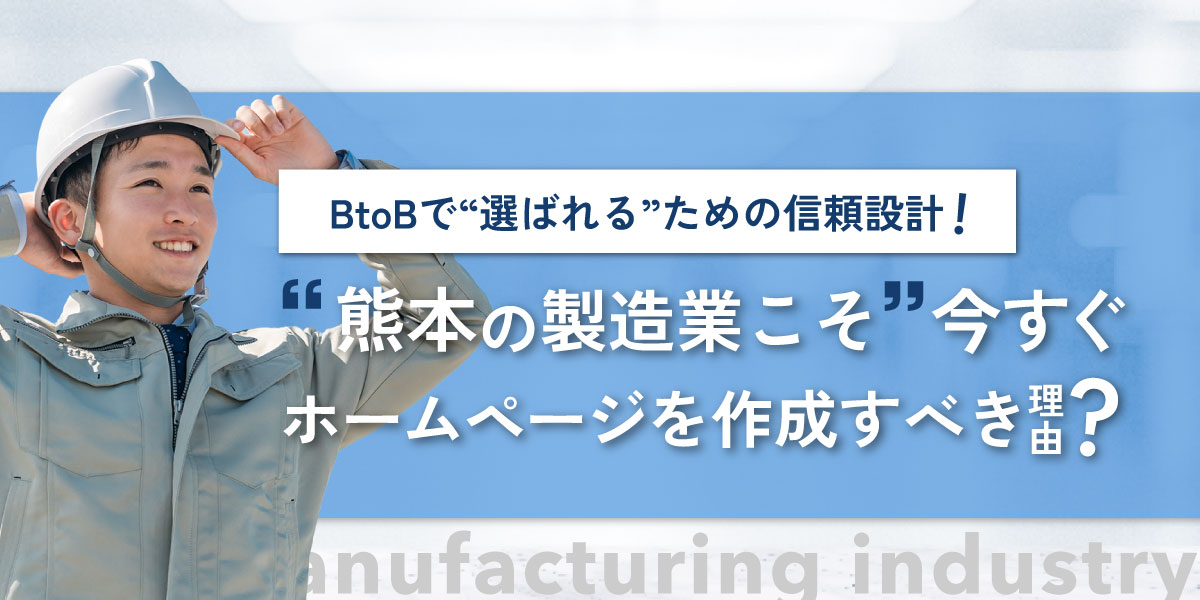NEWS&COLUMN
お知らせ&コラム
2025.05.07
ホームページ制作は“更新のしやすさ”で選ぶ!-中小企業向け運用方法と成功の秘訣-
- #SEO対策
- #ホームページ
はじめに|ホームページは「作って終わり」じゃない
中小企業が新たにホームページを作るとき、最も見落とされがちなのが「更新しやすさ」です。
多くの企業が、見た目のデザインや初期費用、制作期間ばかりに目を向けがちです。
けれど、本当に重要なのは「完成後にどう運用するか」。
作って終わりの時代はもう終わりました。
検索結果で上位に表示されるホームページには、ある共通点があります。
それは「継続的に更新されていること」です。
Googleは“生きているサイト”を高く評価します。
逆に、数年放置されたサイトは、検索エンジンにもユーザーにも相手にされません。
また、企業の信頼性にも関わります。「お知らせ」の最終更新日が3年前。
SNSのリンク先がエラー。スタッフ紹介が前任者のまま…
こうした細かい部分が積み重なると、「この会社、大丈夫かな?」という印象を与えかねません。
そこで必要になるのが、“自社で更新できる”ホームページの仕組みづくりです。
わざわざ業者に頼まなくても、社内で簡単に情報を追加・編集できる。この体制が整えば、タイムリーな情報発信が可能になり、ホームページは“攻めのツール”へと変わります。
この記事では、ホームページ制作時に知っておくべき「更新性」の重要性、自社で運用するための具体的な方法、注意すべきポイントなどを、中小企業向けにわかりやすく解説していきます。
ホームページ制作で失敗しがちなポイント
見た目重視の落とし穴
ホームページ制作でよくある失敗のひとつが、デザインに注力しすぎて、更新性を置き去りにしてしまうことです。
たしかに、洗練されたデザインは企業イメージの向上につながります。しかし、見た目にこだわるあまり、更新が難しい構造になっているケースが後を絶ちません。管理画面にログインしても、どこを編集すればよいかわからない。コードをいじらないと文言一つ変えられない。これでは、社員が更新作業を続けられるはずもありません。
更新依頼が業務の足かせに
「制作会社に頼めばいい」と考える経営者も多いでしょう。実際、細かい部分まで外注すれば、ミスのリスクも減ります。しかし、更新のたびに見積もりを取り、修正依頼をし、確認のやり取りをして…と手間がかかります。結果、「それくらいなら放っておこう」となり、サイトは次第に情報が古びていくのです。
社内の属人化が招く更新停止
もうひとつ見落とされがちなリスクが、「担当者への依存」です。
たとえば、Webに詳しい社員に任せきりにしていた場合、その人が退職・異動すれば更新が止まってしまいます。管理方法が引き継がれておらず、ログイン情報すら分からないという事態も。これは特に中小企業で頻繁に起こります。
ホームページ更新方法とは?
「更新する」とは何を指すのか
ホームページの更新とは、具体的にどのような作業を指すのでしょうか。
主に次のようなものがあります:
◼︎お知らせの追加・変更
◼︎採用情報の掲載内容更新
◼︎商品・サービス情報の修正
◼︎スタッフ紹介の入れ替え
◼︎ブログの投稿
こうした作業が日常的に発生する場合、「自社で更新できるかどうか」が非常に重要になります。
CMSとは?初心者でも扱えるツール
最近では、HTMLやCSSの知識がなくてもホームページを更新できる仕組みとして「CMS(コンテンツマネジメントシステム)」の導入が主流です。
なかでも代表的なのがWordPress。世界中のWebサイトの40%以上がこの仕組みで運用されています。使い方はブログに近く、「タイトル」「本文」「画像」を管理画面から入力するだけで、整ったページが簡単に作れます。
ノーコードで更新できる時代
CMSを導入すれば、専門知識がなくても運用できます。たとえば、営業担当者が今日のイベント風景をブログとして投稿したり、事務スタッフがキャンペーン情報をトップページに反映したり。現場の声がリアルタイムに届くサイトに育てることができます。
自社で更新できるメリット
タイムリーな情報発信
ホームページを自社で更新できる最大の利点は、スピードです。
飲食店なら「今週のランチメニュー」。美容室なら「空き状況のお知らせ」。建築会社なら「最新の施工事例」。情報の“鮮度”が命の業種では、更新が即日でできる体制は欠かせません。
社内で操作できる体制が整っていれば、こうした更新がその日のうちに反映されます。
SEO対策としての「鮮度」
検索エンジンは、定期的に更新されているサイトを評価します。これはGoogleの公式見解でもあります。
「更新されていない=古い情報」「放置されている=信頼性が低い」と判断される恐れもあります。逆に、こまめな更新があれば、検索順位にプラスの影響が期待できます。
とくにブログ更新や事例紹介は、SEOに強いコンテンツです。社内で日々の出来事を記事化するだけで、検索経由の流入が増えていくのです。
コスト面での大きな違い
更新を外注すると、1回につき数千〜数万円かかることがあります。毎月3〜4件の更新が発生すれば、年間では数十万円にのぼることも。
一方、自社更新に切り替えれば、これらの費用は基本的にゼロになります。もちろん、最初は慣れが必要ですが、長期的には大きなコスト削減になります。
自社らしさを伝える力
外注ライターに書いてもらう文章と、社内の担当者が書いた文章では、どうしても“空気感”が異なります。
社員自身が発信することで、企業の価値観や雰囲気がより伝わるサイトになります。たとえば、施工現場の写真に一言添えるだけでも、「こんな仕事をしているんだな」というイメージが強く伝わります。
自社の声を自社で届けられること。それこそが最大の“強み”になるのです。
自社更新の注意点と対策
更新ルールの整備
自社で誰でも更新できるようになると、「自由すぎる」ことで起きるトラブルもあります。
◼︎フォントサイズがバラバラ
◼︎画像の比率が崩れて表示が乱れる
◼︎色や文体が統一されていない
こうした問題は、見た目の印象だけでなく、ユーザーの信頼感にも影響します。
そのため、更新ルールのマニュアル化が不可欠です。どのサイズの画像を使うのか、文字数は何文字を目安にするのか、用語の統一はどうするのか。初めての人でも迷わず投稿できる基準を社内で決めておきましょう。
セキュリティの管理と保守
WordPressなどのCMSは便利ですが、定期的なメンテナンスを怠るとセキュリティリスクが高まります。
◼︎管理画面のパスワードが初期設定のまま
◼︎プラグインが古くて脆弱性がある
◼︎CMSのバージョンアップが未実施
これらを放置すると、サイトが改ざんされたり、スパムの踏み台にされたりする危険性があります。
更新は社内、保守やバックアップは外部に任せるという体制がおすすめです。
担当者任せにしない仕組みづくり
「この人しか更新できない」では、いざという時に困ります。中小企業の場合、1人の担当者に依存してしまいがちですが、これは非常に危険です。
複数人で更新できるよう、教育・引き継ぎ・マニュアル整備をしっかり行いましょう。
更新しやすい制作のポイント
管理画面の設計がカギ
「誰でも使える」ホームページを作るためには、管理画面のシンプルさが必要です。
メニューは日本語でわかりやすく。項目名は「会社情報」「新着情報」など直感的に。よく使う編集箇所には説明文や画像サイズのガイドを表示する。こうした工夫が、社内の更新をスムーズにします。
更新パターンをテンプレート化
「毎回レイアウトを作る」のは現実的ではありません。よく使うパターンはあらかじめ設計しておくのがポイントです。
- お知らせ投稿テンプレート
- 実績紹介ページの構成
- スタッフ紹介のフォーム
このような“型”があれば、文章や写真を差し替えるだけで簡単にページが完成します。
サポートが受けられる制作会社を選ぶ
「更新は自社で」とはいえ、トラブル時にはプロの助けが必要です。
だからこそ、納品後のサポート体制が整った制作会社を選ぶことが大切です。電話・メールでの対応、緊急時の復旧支援、年1回の運用チェックなど、伴走型のパートナーがいれば安心です。
まとめ|ホームページは“育てる時代”へ
ホームページは、ただ“ある”だけでは意味がありません。
これからの時代、どれだけ情報を発信できるか、どれだけ使いやすいかが問われます。
更新できる仕組みさえ整っていれば、社員が発信した記事が検索にヒットし、新しい顧客との接点が生まれます。会社の最新情報を伝えることで、信頼感や関心も高まります。
制作時に「更新性」という視点を持つこと。そして、自社での運用体制を整えること。それが、これからの中小企業のホームページに求められるスタンダードです。
有限会社テイク・シーにご相談を!
有限会社テイク・シーでは、webサイトからチラシやパンフレットなどの紙媒体まで、さまざまな広告物をサポートいたします。お気軽にお問い合わせくださいませ!