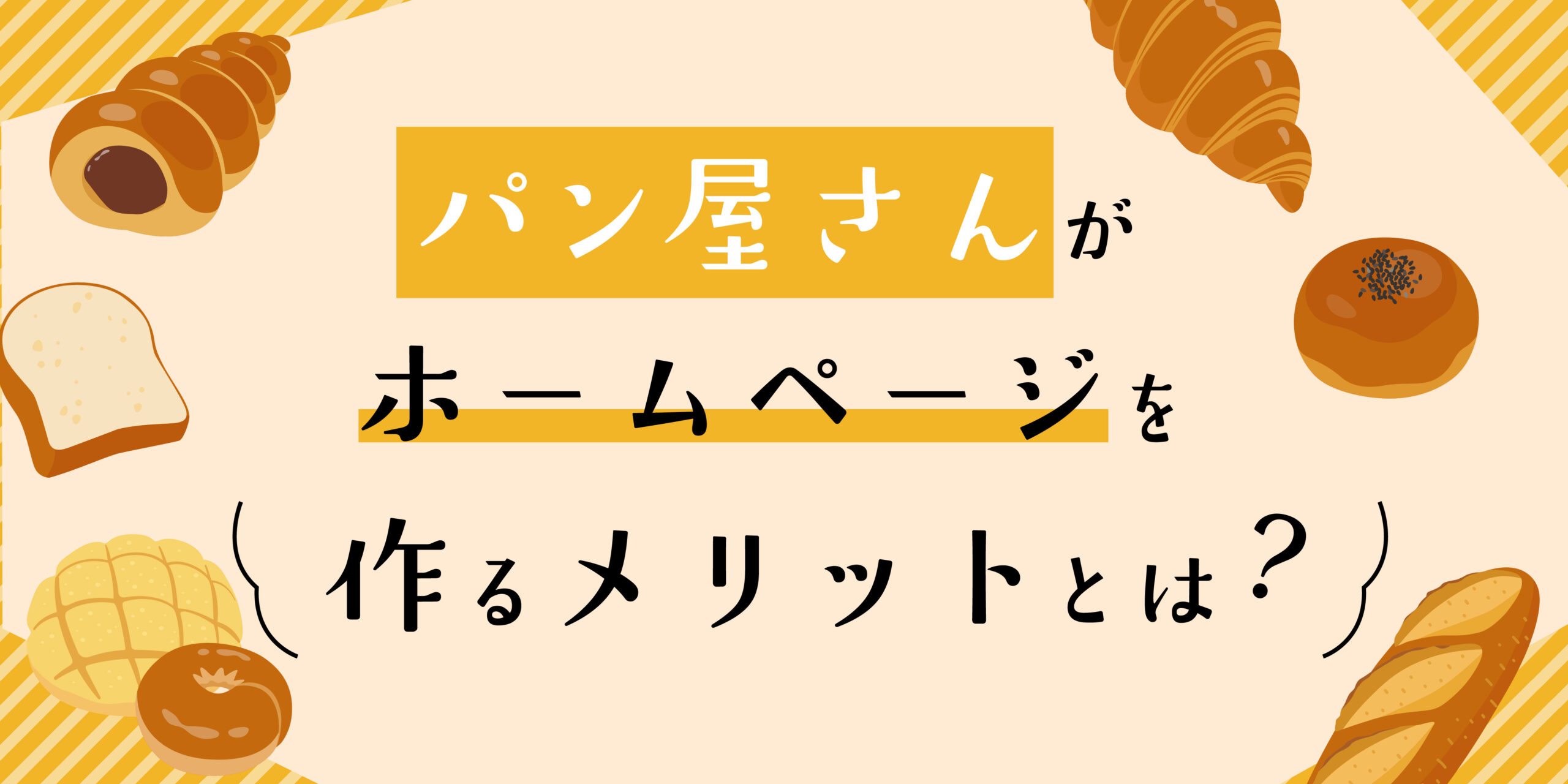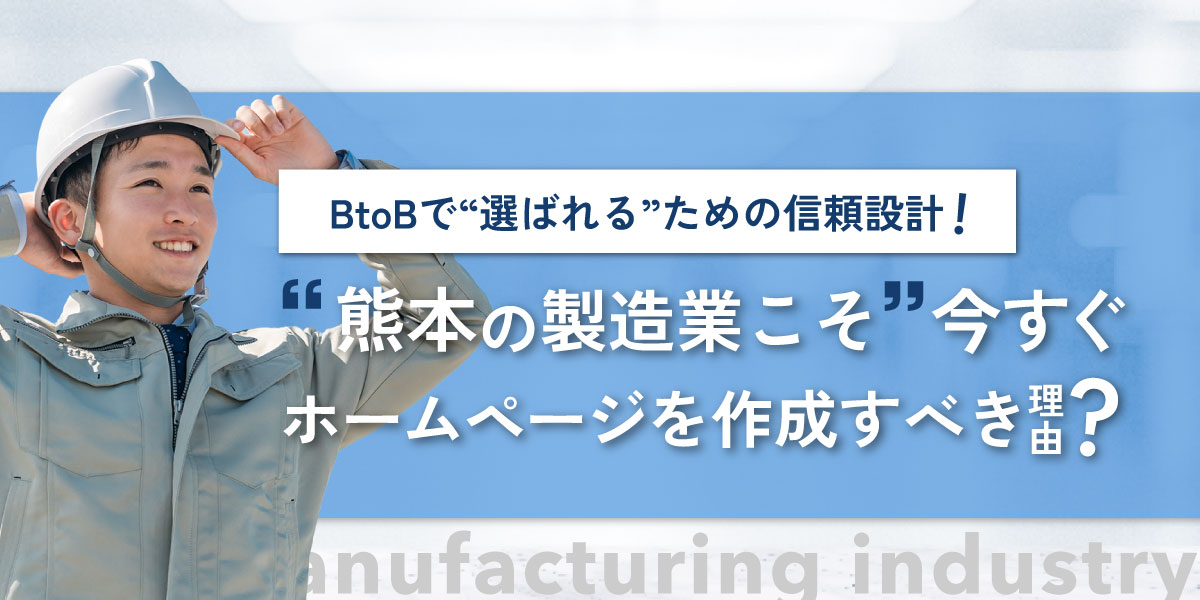NEWS&COLUMN
お知らせ&コラム
2025.05.22
【2025年最新版】福祉業界こそホームページを持つべき理由
- #SEO対策
- #コラム
- #ホームページ

今日は「福祉業界がホームページを持つべき理由」について、一緒に考えてみたいと思います。
というのも、保育園や幼稚園と同様に、介護施設や障がい者支援などの福祉サービスでも、まだまだ「紙のパンフレットだけ」「紹介に頼っている」という事業者さんが少なくありません。
けれど今、福祉の現場こそホームページが必要な時代になってきています。
今回は、福祉事業所がホームページを作ることの大切さについて、わかりやすくお話ししていきますね。
1.利用者が「施設を選ぶ時代」になっている
まず最初にお伝えしたいのは、今の福祉サービスは「選ばれる時代」だということです。
高齢者施設、グループホーム、就労支援事業所…いまや地域にたくさんの選択肢があります。利用者や家族はその中から、できるだけ自分たちに合った施設を選ぼうとします。
では、どうやって情報を探すのでしょうか?
答えは、インターネットです。
Googleで「〇〇市 デイサービス」「障がい者 グループホーム」などと検索して、施設の情報を比較する──これは今やごく普通の行動です。
にもかかわらず、ホームページがない。
あっても情報が古くて、「いつのデータ?」と思ってしまう。
これでは、「選ばれる」以前に、見つけてもらえないのです。
さらに、検索エンジンに表示される順番も重要です。施設の情報が他のポータルサイトの中に埋もれてしまっていると、せっかく魅力的なサービスを提供していても、検索する人の目に留まりません。自社ホームページを持つことで、検索エンジン最適化(SEO)にも取り組むことができ、上位表示の可能性が高まります。また、スマートフォンで調べる方も増えているため、スマホ対応のレスポンシブデザインにすることで、より多くの人に見てもらえるようになります。
2.ホームページは「安心」の入り口
福祉業界にとって、信頼感は何より大切です。
介護も障がい福祉も、利用者本人やその家族にとっては「生活の一部」になるサービス。だからこそ、誰もが不安や疑問を抱えながら施設を探しています。
たとえば、こんな気持ちに寄り添ってあげられるのが、ホームページの役割です。
・どんな雰囲気の施設なのか知りたい
・スタッフはどんな人?
・食事は? 入浴は? プライバシーは?
・自分に合っているサービスか判断したい
ホームページに、写真やサービス内容、スタッフの想いがきちんと掲載されていれば、それだけで安心感につながります。
逆に、情報がなければ「ちょっと不安だな」と思われてしまうかもしれません。
とくに、利用者の声や家族からのコメントを掲載することで、リアルな評価が伝わりやすくなります。施設の理念やケア方針など、言葉にして伝えることも信頼性につながりますし、実際に働くスタッフの表情がわかる写真や、日々の活動内容をブログ形式で更新することで、「見える運営」が実現できます。情報が透明であることは、利用者にとっての安心材料であると同時に、事業所としての信頼を築く第一歩になります。
3.スタッフ採用にもホームページは効く
実は今、福祉業界で大きな課題となっているのが人材確保です。
「応募が来ない」「来ても定着しない」という声は、全国どこでも聞かれます。
ここでもホームページが重要なカギを握っています。
求職者の多くは、応募の前に必ずネットで施設を調べます。
そのときに、ホームページがあるかないかで、印象は大きく変わります。
・スタッフ紹介やインタビューが載っている
・現場の様子が写真でわかる
・理念やビジョンがきちんと伝わってくる
こうした内容があることで、「ここで働いてみたい」という気持ちにつながります。
求人情報サイトに載せるだけでなく、自社のホームページで魅力を発信することが、これからの採用には欠かせません。
また、福利厚生や研修制度、キャリアパスについての情報を詳しく掲載することも、求職者にとって非常に有益です。現場の声を取り入れたブログ記事や動画コンテンツを通じて、職場の雰囲気をリアルに伝えることができます。「こんな環境で働けるなら安心」と感じてもらえることで、採用のミスマッチを防ぎ、定着率の向上にもつながります。採用に力を入れたい施設こそ、しっかりとした採用コンテンツを持つことが重要です。
4.「紙」だけでは伝わらないことがある
地域包括支援センターや病院など、他の機関から紹介を受けることも多い福祉サービス。
もちろん、パンフレットや名刺、紹介状も大切なツールですが、それだけでは限界があります。
なぜなら、「伝えられる情報量に限りがある」からです。
紙面では数行しか書けないことでも、ホームページなら、
・サービス内容の詳しい説明
・写真や動画での施設紹介
・実際の利用者の声やQ&A
など、より深く、豊かに伝えることができます。
とくに、写真や動画は施設の雰囲気をダイレクトに伝えられるので、信頼感を生む要素としてとても効果的です。
また、パンフレットは一度配ってしまえば情報の更新が難しいのに対し、ホームページであれば必要に応じていつでも内容の変更が可能です。たとえば、新しく始めたサービス、キャンペーン、料金体系の変更、スタッフの追加情報などもタイムリーに掲載できます。加えて、PDF形式のパンフレットやリーフレットをダウンロードできるようにしておくことで、「紙」と「Web」の両方のメリットを活かすことが可能になります。
5.福祉サービスこそ「地域とのつながり」を育てる
福祉施設は、地域の中で人と人とを結ぶ役割も担っています。
だからこそ、地域の方に「こんな施設がありますよ」と伝えたり、「地域とこんな取り組みをしています」と発信することが、とても大切です。
ホームページは、そうした地域との接点を生み出す場にもなります。
たとえば、
・地域の子どもたちとの交流イベント
・夏祭りや作品展のお知らせ
・利用者の方の日常の笑顔を発信
そんな温かい日常を紹介することで、「この施設、素敵だね」「うちのおばあちゃんにも合いそう」と、地域からの信頼や親しみが自然と広がっていくのです。
さらに、地域のボランティア募集や地域資源との連携活動なども掲載することで、双方向のつながりが生まれやすくなります。地元の学生との福祉体験活動や、地域包括ケアの一環としての役割紹介など、施設が“地域のハブ”として機能していることを発信することで、より多くの人の理解と共感を得ることができます。「あの施設は地域に開かれている」という評価が広がれば、自然と人が集まり、施設の価値が高まります。
6.「ホームページ×SNS」の相乗効果
最近では、InstagramやFacebookを活用する福祉施設も増えてきました。
もちろん、SNSも有効なツールですが、やはり「公式な情報の受け皿」として、ホームページは欠かせません。
SNSで日常の風景を投稿し、興味を持った人がホームページで詳しく情報を見る。
この流れが自然にできると、情報発信の導線としてとても強力です。
また、Google検索の際にヒットするのはSNSよりも圧倒的に「ホームページ」。
SEO対策(検索で上位表示される工夫)という意味でも、福祉施設のホームページには大きな価値があります。
7.「お問い合わせ」の窓口をつくる
ホームページがあることで、問い合わせがしやすくなるというメリットもあります。
電話番号や住所だけでなく、
・お問い合わせフォーム
・資料請求のボタン
・よくある質問ページ(FAQ)
などを用意しておくことで、利用希望者や家族、求職者が気軽に連絡を取りやすくなります。
「ちょっと話を聞いてみたい」――そんな最初の一歩をサポートできるのが、ホームページなんです。
福祉の現場こそ、顔を見せよう
福祉は、人と人のつながりの仕事です。
そのあたたかさや誠実さを、もっとたくさんの人に届けるために。
そして、必要な人に必要な支援を届けるために。
ホームページは、**あなたの施設の“顔”**となる存在です。
「難しそう」「時間がない」「費用が心配」
そんな気持ちがあるかもしれません。でも、まずは一歩踏み出してみませんか?
大切なのは、「何をどう伝えたいか」を明確にすること。あなたの想いを、きちんと届ける手段として、ホームページはとても心強い味方になります。
「ホームページを持っていない福祉施設さんに、この記事が届けばいいな」
そんな想いを込めて、今回はお届けしました。
有限会社テイク・シーでは、webサイトからチラシやパンフレットなどの紙媒体まで、さまざまな広告物をサポートいたします。お気軽にお問い合わせくださいませ!
あなたの施設が、もっと多くの人に届きますように。